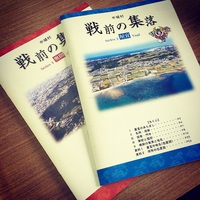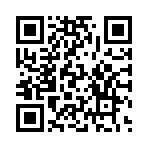2009年06月23日
命どぅ宝
命どぅ宝(ぬちどぅたから)
この季節はこの言葉を良く聞きますよね。
今日は慰霊の日。
慰霊の日関連で沖縄戦に関することを書いたブログも多いでしょうが、
ここはひとつ、趣を変えて「命どぅ宝」という言葉の元ネタについて書きたいと思います。
さて、この「命どぅ宝」ですが、読んで字のごとく、「命こそ宝」という意味です。
「生きてこそ」という意味ですね。
先日、大先輩であるS氏より、その出典についてお話を聞きました。
(正直、その話を聞くまでは「命どぅ宝」の出典なんて考えたことなかったんですが)
この言葉の元ネタは一般的に、
尚寧王が琉歌で
「戦さ世んしまち みるく世ややがて 嘆くなよ臣下 命どぅ宝」と詠んだとか
(でもぶっちゃけ、その当時に八・八・八・六の琉歌が成立していたか不明らしい)
尚泰王が琉歌で
「戦さ世んしまち みるく世ややがて 嘆くなよ臣下 命どぅ宝」と詠んだとされており、
(でも、実はこの琉歌は後世に作られた戯曲が元ネタらしい)
ウィキペディアには
尚泰王の遺した琉歌がその由来とされこともあるが、
本来は戦争について訴える演劇中のセリフである。
と載っており、
琉球新報社の『沖縄コンパクト事典』には
出典は琉歌の「戦さ世んしまち みるく世ややがて 嘆くなよ臣下 命どぅ宝」
と載っています。
以上のように、由来には諸説あって意見が定まっていません・・・
ちなみに、沖縄サミットの時にクリントンは演説の中で
「命どぅ宝」を引用し、尚泰王が詠んだものとしたそうです(笑)
さて、S氏によると、「命どぅ宝」という言葉は
組踊の「屋慶名大主敵討」の台詞に出てくるとのこと。
県が出している『沖縄県史料 前近代8 芸能1 (組踊)』でも確認できます。
S氏はこの県史料を編集した方から教えてもらったと言ってました。
はっきりと元ネタと断言できるわけではないですが、
近世の組踊の中に「命どぅ宝」という台詞が確認できるので、
少なくとも近世までは遡れるということです。
ということは、上で挙げた尚泰王が出典である、
戦後の演劇が出典である、というのは違ってきますね。
また、史実として尚泰王が詠んだという話がまかり通っていることは、
ちょっとまずいかな~と感じました。
尚寧王が詠んだ、という話は「戦→島津侵攻→尚寧王」という連想ゲームでしょうね。
マスメディアが創作と史実とを区別できてない傾向があるんで、
しょうがないかなぁとも思いますが・・・。
話は意味くじわからんところに流れてしまいました。すいません
ではでは、今日も平和な一日に感謝して・・・。
文責:saku
この季節はこの言葉を良く聞きますよね。
今日は慰霊の日。
慰霊の日関連で沖縄戦に関することを書いたブログも多いでしょうが、
ここはひとつ、趣を変えて「命どぅ宝」という言葉の元ネタについて書きたいと思います。
さて、この「命どぅ宝」ですが、読んで字のごとく、「命こそ宝」という意味です。
「生きてこそ」という意味ですね。
先日、大先輩であるS氏より、その出典についてお話を聞きました。
(正直、その話を聞くまでは「命どぅ宝」の出典なんて考えたことなかったんですが)
この言葉の元ネタは一般的に、
尚寧王が琉歌で
「戦さ世んしまち みるく世ややがて 嘆くなよ臣下 命どぅ宝」と詠んだとか
(でもぶっちゃけ、その当時に八・八・八・六の琉歌が成立していたか不明らしい)
尚泰王が琉歌で
「戦さ世んしまち みるく世ややがて 嘆くなよ臣下 命どぅ宝」と詠んだとされており、
(でも、実はこの琉歌は後世に作られた戯曲が元ネタらしい)
ウィキペディアには
尚泰王の遺した琉歌がその由来とされこともあるが、
本来は戦争について訴える演劇中のセリフである。
と載っており、
琉球新報社の『沖縄コンパクト事典』には
出典は琉歌の「戦さ世んしまち みるく世ややがて 嘆くなよ臣下 命どぅ宝」
と載っています。
以上のように、由来には諸説あって意見が定まっていません・・・

ちなみに、沖縄サミットの時にクリントンは演説の中で
「命どぅ宝」を引用し、尚泰王が詠んだものとしたそうです(笑)
さて、S氏によると、「命どぅ宝」という言葉は
組踊の「屋慶名大主敵討」の台詞に出てくるとのこと。
県が出している『沖縄県史料 前近代8 芸能1 (組踊)』でも確認できます。
S氏はこの県史料を編集した方から教えてもらったと言ってました。
はっきりと元ネタと断言できるわけではないですが、
近世の組踊の中に「命どぅ宝」という台詞が確認できるので、
少なくとも近世までは遡れるということです。
ということは、上で挙げた尚泰王が出典である、
戦後の演劇が出典である、というのは違ってきますね。
また、史実として尚泰王が詠んだという話がまかり通っていることは、
ちょっとまずいかな~と感じました。
尚寧王が詠んだ、という話は「戦→島津侵攻→尚寧王」という連想ゲームでしょうね。
マスメディアが創作と史実とを区別できてない傾向があるんで、
しょうがないかなぁとも思いますが・・・。
話は意味くじわからんところに流れてしまいました。すいません

ではでは、今日も平和な一日に感謝して・・・。
文責:saku
Posted by シマミグイ at 21:29│Comments(4)
│日常
この記事へのコメント
はじめまして、興味深く拝見しました。
「命どぅ宝」の出典ですが、ずっと山里永吉『首里城明渡し』だと思っていました。クリントン大統領が尚泰史実説に言及したことに反論して、琉球新報に大城立裕先生が寄稿された≪「命どぅ宝」異聞http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-115445-storytopic-86.html≫によると、琉球処分を主題にした山里作品のひとつ『那覇四町昔気質』とのことです。「首里城―」の幕切れに「那覇四町―」が混入したと仲程昌徳≪「首里城明渡し」小論≫にあります。また、尚寧王説は真境名由康の『国難』にもあります。
『首里城』は大ヒットしましたし、大城先生が琉歌の作者と推察されている伊良波尹は、尚泰王そのままとの評判だったといいます。終戦後も好評を得ました。
≪常に政争の具にされてきたことへの痛恨の思いが重ねられたことにあるといっていいだろうが、戦後の再演が感動を呼んだのは、あと一つ、最後の場面と関わりがあったのではなかろうか。烈しい爆撃のなかを生き残った人たちが身にしみて知ったのは他でもなく「命どう宝」ということであった。王国の滅亡を目の前にして歌われた歌のその一言は、別の思いをともなって戦後の観客の胸に響いたに違いないからである≫(山里)
ことを考えると、「命どぅ宝」が人口に膾炙するきっかけはい山里作品だと考えていいのではないでしょうか。
『屋慶名大主敵討』にある「命どぅ宝」は、横恋慕から夫を殺された「をなじゃら」が敵の屋慶名大主に迫られたのを拒んで、命を奪われそうになったときに、屋慶名の配下が≪命ど宝 短気腹立ちや 怪我の基ひ≫と身を任せるように働きかける場面で使われます。
平和のスローガンの出典としては、あまりいい場面ではありませんし、長く埋もれていた作品です。(大城先生の推論に従うなら、伊良波の脳裏をかすめたかもしれませが)。
ということで、厳密な「出典」かどうかはともかくとして、「広まるきっかけ」は沖縄芝居だと私は考えています。
ながながとすいません。本当にはっきりわかるといいですね。
「命どぅ宝」の出典ですが、ずっと山里永吉『首里城明渡し』だと思っていました。クリントン大統領が尚泰史実説に言及したことに反論して、琉球新報に大城立裕先生が寄稿された≪「命どぅ宝」異聞http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-115445-storytopic-86.html≫によると、琉球処分を主題にした山里作品のひとつ『那覇四町昔気質』とのことです。「首里城―」の幕切れに「那覇四町―」が混入したと仲程昌徳≪「首里城明渡し」小論≫にあります。また、尚寧王説は真境名由康の『国難』にもあります。
『首里城』は大ヒットしましたし、大城先生が琉歌の作者と推察されている伊良波尹は、尚泰王そのままとの評判だったといいます。終戦後も好評を得ました。
≪常に政争の具にされてきたことへの痛恨の思いが重ねられたことにあるといっていいだろうが、戦後の再演が感動を呼んだのは、あと一つ、最後の場面と関わりがあったのではなかろうか。烈しい爆撃のなかを生き残った人たちが身にしみて知ったのは他でもなく「命どう宝」ということであった。王国の滅亡を目の前にして歌われた歌のその一言は、別の思いをともなって戦後の観客の胸に響いたに違いないからである≫(山里)
ことを考えると、「命どぅ宝」が人口に膾炙するきっかけはい山里作品だと考えていいのではないでしょうか。
『屋慶名大主敵討』にある「命どぅ宝」は、横恋慕から夫を殺された「をなじゃら」が敵の屋慶名大主に迫られたのを拒んで、命を奪われそうになったときに、屋慶名の配下が≪命ど宝 短気腹立ちや 怪我の基ひ≫と身を任せるように働きかける場面で使われます。
平和のスローガンの出典としては、あまりいい場面ではありませんし、長く埋もれていた作品です。(大城先生の推論に従うなら、伊良波の脳裏をかすめたかもしれませが)。
ということで、厳密な「出典」かどうかはともかくとして、「広まるきっかけ」は沖縄芝居だと私は考えています。
ながながとすいません。本当にはっきりわかるといいですね。
Posted by はりくやまく at 2009年07月02日 03:02
コメントありがとうございます。
返信が遅れて申し訳ございません・・・。
7月はいろいろと忙しかったもので・・・。
さて、「命どぅ宝」ですが、私もはりくやまくさん同様、「広まるきっかけ」は沖縄芝居だと考えています。
出典はさておき、「命どぅ宝」の言葉自体は流行語のような感じで芝居から広がっていったのかなと想像しております。
しかし、当の芝居を演じる当事者たちは、「屋慶名大主敵討」の「命ど宝」を知っていたんじゃないかと睨んでいます。
伊良波尹吉も知っていたんじゃないでしょうか。
それから、大城立裕先生の記事ですが、実は上記の「S氏」こと新城栄徳氏が約一ヵ月後に補足の記事を書いています。本人から新聞のコピーをいただいて、上記の話を教えていただきました(笑)
ネット版には掲載されていないんですが、2000年8月30日の琉球新報に載っています。
何面かまでは失念してしまいました。すいません。
ぜひご覧になってください。
実は文学も芸能も全くの素人なんですが、近代的なイメージのある「命どぅ宝」という言葉が、近世の組踊りの台本に出てくるって面白いなと思い、この記事を書きました。
少なくとも、私は新城氏からこの話を聞くまでは、戦後に生まれた言葉と思っていました・・・。
言葉ひとつからいろいろな歴史を紐解けて面白いですよね。
これからもよろしくおねがいします。
返信が遅れて申し訳ございません・・・。
7月はいろいろと忙しかったもので・・・。
さて、「命どぅ宝」ですが、私もはりくやまくさん同様、「広まるきっかけ」は沖縄芝居だと考えています。
出典はさておき、「命どぅ宝」の言葉自体は流行語のような感じで芝居から広がっていったのかなと想像しております。
しかし、当の芝居を演じる当事者たちは、「屋慶名大主敵討」の「命ど宝」を知っていたんじゃないかと睨んでいます。
伊良波尹吉も知っていたんじゃないでしょうか。
それから、大城立裕先生の記事ですが、実は上記の「S氏」こと新城栄徳氏が約一ヵ月後に補足の記事を書いています。本人から新聞のコピーをいただいて、上記の話を教えていただきました(笑)
ネット版には掲載されていないんですが、2000年8月30日の琉球新報に載っています。
何面かまでは失念してしまいました。すいません。
ぜひご覧になってください。
実は文学も芸能も全くの素人なんですが、近代的なイメージのある「命どぅ宝」という言葉が、近世の組踊りの台本に出てくるって面白いなと思い、この記事を書きました。
少なくとも、私は新城氏からこの話を聞くまでは、戦後に生まれた言葉と思っていました・・・。
言葉ひとつからいろいろな歴史を紐解けて面白いですよね。
これからもよろしくおねがいします。
Posted by saku at 2009年08月04日 23:18
尚寧王期【1589〜1620】に琉歌はすでに成立しているでしょう。
おそらく、琉歌は1609年の薩摩侵攻以降、和文化の影響化の下で成立だと考えたのでしょう。それは琉歌の大成期だと思います。
実際に、尚寧王妃あおりやえが大和に連行された王を思い詠んだとされる琉歌があります。
北風の真北 吹きつめてをれば
按司添前てだの 御船ど待ちよる
綺麗な8.8.8.6 三十音の形になっています。
おそらく、琉歌は1609年の薩摩侵攻以降、和文化の影響化の下で成立だと考えたのでしょう。それは琉歌の大成期だと思います。
実際に、尚寧王妃あおりやえが大和に連行された王を思い詠んだとされる琉歌があります。
北風の真北 吹きつめてをれば
按司添前てだの 御船ど待ちよる
綺麗な8.8.8.6 三十音の形になっています。
Posted by 春日 at 2016年03月18日 03:39
尚寧王期【1589〜1620】に琉歌はすでに成立しているでしょう。
おそらく、琉歌は1609年の薩摩侵攻以降、和文化の影響化の下で成立だと考えたのでしょう。それは琉歌の大成期だと思います。
実際に、尚寧王妃あおりやえが大和に連行された王を思い詠んだとされる琉歌があります。
北風の真北 吹きつめてをれば
按司添前てだの 御船ど待ちよる
綺麗な8.8.8.6 三十音の形になっています。
おそらく、琉歌は1609年の薩摩侵攻以降、和文化の影響化の下で成立だと考えたのでしょう。それは琉歌の大成期だと思います。
実際に、尚寧王妃あおりやえが大和に連行された王を思い詠んだとされる琉歌があります。
北風の真北 吹きつめてをれば
按司添前てだの 御船ど待ちよる
綺麗な8.8.8.6 三十音の形になっています。
Posted by 春日 at 2016年03月18日 03:39